こんにちは。土木公務員ブロガーのカミノです。
学生の皆さん、就職活動いかがでしょうか?
コロナ禍ですから企業側も学生さんもかなり大変だと思います( ゚Д゚)
今回は、そんな就活生のために役立つ1つの就活体験記をご紹介します。
就活生に読んでほしい就活体験記
私が就活生に読んでほしい体験記は、こちらのブログになります↓↓
一般的なブログで、就活に関しての記事はこの3つだけですが、これを読んだとき衝撃を受けました。
記事中では「一般人」と自称していますが、その一般人が、東京の学歴・家柄エリートやコミュ力おばけたちと同じ舞台に立ち、一流企業に採用されるために何を考え何を実行したのか、本質を突いたその技術がわかりやすく綴られています。
体験記を書いたのは…
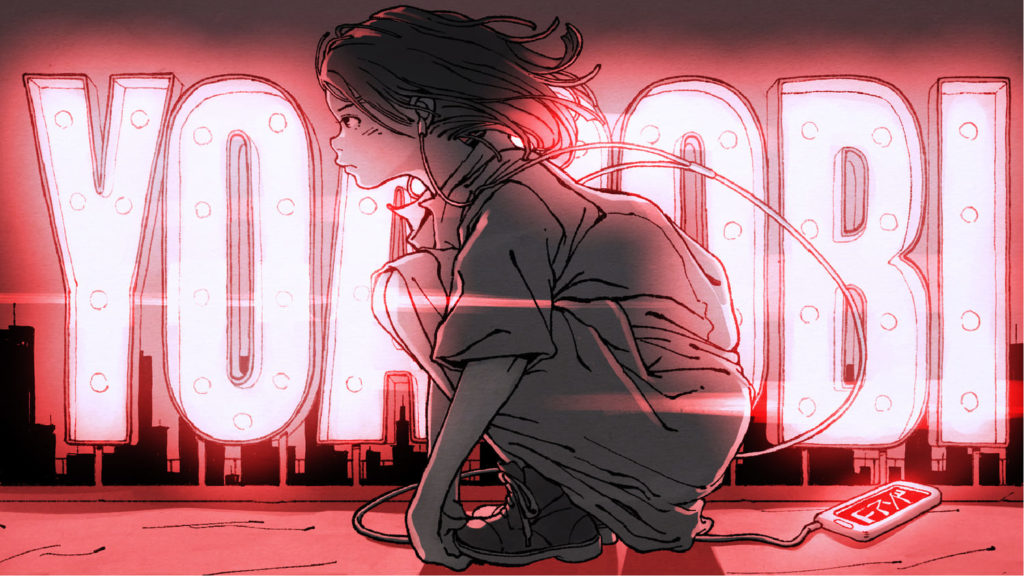
この体験記の筆者は、YOASOBIプロジェクトを起ち上げた若手のプロデューサーです。
YOASOBIめっちゃいいですよね。私も大好きです。2020年から音楽業界のトップを走り続ける音楽ユニット。このプロデューサーさんは、作曲者のAyaseと一緒にYOASOBIの曲を作り上げてる人なので、「ニーズを分析する力」と「魅力を届ける演出力」はやはり突出していると思います。
そんな彼が書いた株式会社ソニー・ミュージックエンターテイメントに就職するまでの記録はすごく役に立つはずです。読んでいただくとわかりますが、この方はほんとに私たちと同じ「一般人」だと思います。
この就活体験記のポイント
先述の就活体験記に書かれているポイントをまとめてみます。
「面接官」だけでなく「受験者」を意識する
まず、エントリーシートの段階で数多の競争相手に打ち勝つ必要があります。面接官は誰でも意識するものです。それだけでなく、「周りの受験者」も競争相手として強く意識しましょう。
例えば、商社であったら
TOEICが満点近くて、
世界中訪れた事があって、
コミュニケーション力も非常に高い。
そんな人であれば結構内定をとれるかもしれない。
ここで重要な事は、そんなスペックを持つ人なんて
数10万人といる就活生の中を探せば
内定の枠である100人くらいの人数は絶対いるという事。
そのスペックに勝つくらいのESや面接の内容でないと
基本的に内定はない。
高スペックの人たちに勝てるエントリーシートを書くこと。
そして、集団面接での話し方や振る舞い、話の展開の仕方など、相手の良い部分は自分の中に取り入れて悪い部分は自分の中から排除していくべき。とのことです。
地方公務員の面接は民間ほど難しくありません(民間ほどずば抜けた経歴の持ち主はいません)。しっかり準備をすれば大丈夫と思います。

1次試験のときに周りを観察してどんな人がいるか、どんな雰囲気か、確認しておきましょう。
説明会では「心に残った言葉」を書き留める
「心に残った言葉」を出来る限り書きためておく事。
しかも発言者の名前、部署付きで。
僕は説明会とかで最後の方はそれしかやってない。
たくさんの説明会に参加した人ならではの発想だと思います。志望動機に昇華するための素材を説明会で探すということですね。民間企業の説明会はタメになりますので公務員志望の人でも行った方が良いと思いますよ(*’ω’*)
面接で聞かれることはたったの3つ
でも面接は少し考えると意外と単純で、
聞かれる事はなんと3つしかない。「今までやってきた事」
「これからやりたい事」
そして
「志望動機」
就活やってきた人は分かると思うけど
ホントにこの3つしか聞かれない。この3つを色んな角度から、
色んな言い回しで聞いてくるのが面接。
この3つを詰め切ること。
これについては、その通りですね。この3つを準備段階で詰め切る。30分の中で、丁寧に簡潔に、ハキハキと、やる気に満ちて、物腰柔らかに話せれば合格です。
私は受験の時、面接とか深く考えていませんでしたが、面接カードの書き方なんかと一緒に別記事で深堀りしたいと思います。
公務員の面接は簡単?

先述の就活体験記からは民間の熾烈な就職競争を感じ取れたと思いますが、それこそが私が今回一番伝えたいことです。
私は、正直なところ公務員の就活、特に面接はぬるいと思っています。もちろん、国家公務員総合職や倍率100倍を超える国立国会図書館の職員などは別物として。
難易度の感じ方は人それぞれですから、公務員の採用試験は民間企業よりも難しいと考えてる人も多くいますし、その人たちは、筆記試験の勉強量が大変だと思っているようです。たしかに事務職だと専門科目を網羅するのは時間が掛かるし大変そうではありますが、
ただ、この就活体験記のように、大手企業の就職競争と比べると、どうしても「勉強さえしておけばOK」な公務員試験は簡単に感じてしまうのかもしれません。

民間よりマシと思って気持ちを楽にして勉強しましょう_(:3 」∠)_
おわりに
今回紹介した就活体験記の内容は、民間企業用ではありますが、公務員にも使えるものだと思います。特に私が共感した部分については、このブログでも深堀りして、また解説したいと思います。
他人の就活体験記を紹介するのがメインなのでちょっと雑になってしまいましたが、すみません。
では、今日はこのあたりで。
またぬん(*’ω’*)ノシ




コメント